- 2010.01.25
- 経営改善計画書
昨年秋以降の金融庁の
金融検査マニュアル改訂にも見られるように
金融機関の支援前提で
実現可能性がある
経営改善計画書(事業計画書)が策定されていれば
リスケ等の貸出条件緩和先であっても
変更経営が健全化される期間を
原則5年(最長10年)として
不良債権とは扱われない場合があります。
では、実現可能性ある経営改善計画とは
どのようなものなのでしょうか?
その前に
銀行が債務者の経営改善計画書で
「何」が知りたいのか?
これを調べていきましょう。
①今後の借入金の返済がどの程度可能であるのか?
リスケ要請に応じた場合
リスケ期間満了以降の返済が
当初約定どおりの返済が可能か?
ということであり
②また、その返済計画における借入金返済原資として
「税引き後利益+減価償却費」の計画
その背景としての売上計画・経費圧縮等の計画
(以下は個別事情により程度・踏み込み度合いは異なりますが)
その根底としての
事業群・製品群・製品別等に
細分化した売上計画・経費圧縮等の計画
さらに、各細分化した分野ごとの
SWOT(強み・弱み・機会・脅威)を考慮した各損益計画が
ある程度の根拠・具体性・実現可能性があるのか否か、であります。
「実現可能性ある」経営改善計画とは
単なる漠然とした右肩上がりの
バラ色の売上・利益計画では
まったく意味がありません。
言い尽くされた感がある言葉ですが
「強み」を発揮して細分化された経営資源
(ヒト・モノ・カネ)の強い部分を
集中投資することにより
収益力(銀行にとってはそれが返済能力の裏づけ)を
向上させなければなりません。
経営改善計画書において
金融機関の理解・支援を得て
事業再生を成功する為には
結局、「本業の復活・収益構造の改善」に行き着きます。
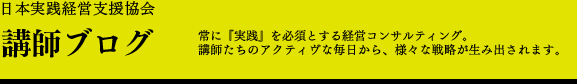
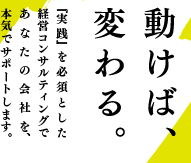
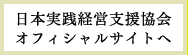
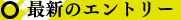
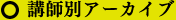
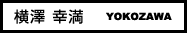
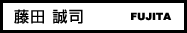
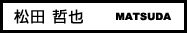
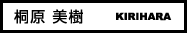
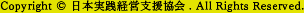

コメントする