- 2010.01.17
- キャッシュベース経営の原則
京セラ名誉会長の稲盛氏は
「儲かったお金はどこにいったのか?」という疑問から
このキャッシュベース経営の重要さに気づいた、と言われています。
確かに決算上は利益が出ているが
その利益に見合ったキャッシュが無い...
そういうことが多いと思います。
いや、ほとんどの会社が、そうなっているはずです。
儲かったお金は
まだ回収できていなかったり(売掛金・受取手形)
次の商品の仕入れに回っていたり(在庫)
設備投資などに使っていたり(固定資産)
さらには借入金の返済に回っていたり(借入金の減)します。
だから、手元にお金がないのです。
これを良くわかっていないと、経営を誤ることになります。
利益だけを見て経営をしていると
「儲かったから、これを買おう、投資しよう、人を入れよう...」
ということになりかねません。
そのようなことをすると、どうなるか?
当然、キャッシュフローが破綻してしまいます。
だからこそ稲盛氏は
最も重要な「キャッシュ」に着目して
それをベースにして
正しい経営判断を行なうべきである、と述べています。
これが、キャッシュベース経営の原則です。
さらに稲盛氏は
一般にある利益から出発して
キャッシュフロー計算書を作るのではなく
経営そのものをキャッシュベースで行なうべきである、と言っています。
すなわち、会計上の利益と
手元のキャッシュとの間に介在するものを
出来るだけ無くすことが必要である、ということです。
たとえば
売上はできるだけ早く回収する、現金化すること。
在庫は極力持たないこと。
在庫の評価はできるだけ下げること。
不良在庫などはすぐに落とすこと。
固定資産にはできるだけ計上せず、費用処理すること。
固定資産に計上した場合は、早期に償却すること。
無借金経営にしていくこと。
また
売掛金などが完全になくならない場合は
同等以上の買掛金や未払金を持っていれば
キャッシュへの影響は少なくなるはずです。
上記のたとえば以降のところは
稲盛氏の本に書いてあるわけではなく
私が勝手に想像して書いていますが。
要は、いかに会計上の利益と
キャッシュフローを合わせていくか
究極は現金主義経営ですね。
すべて現金取引で行なえば
キャッシュベース経営になるわけです。
ただ、近代的な経営では
なかなかそういうわけにはいかないでしょうから
まずは出来るところからやって
後は若干の調整をして見る
ということになるのだと思います。
いずれにせよ、儲かったお金はどこに行っているのか?
これを常に見ておくということが、大事です。
経営判断を誤らないために。
従って、損益計算書だけでなく
常に貸借対照表も見て
お金がどこに行っているのかを
前月・前年と比べて
どの科目が増え、どの科目が減っているのかを見れば
それは大よそつかめてくるはずです。
是非、キャッシュベース経営をやってみてください。
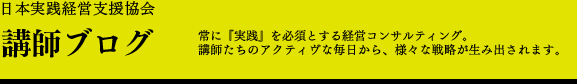
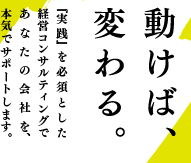
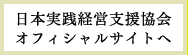
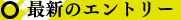
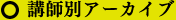
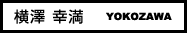
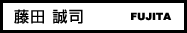
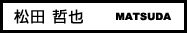
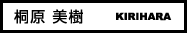
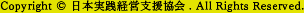

コメントする